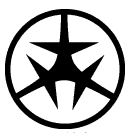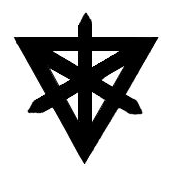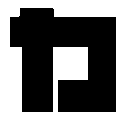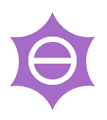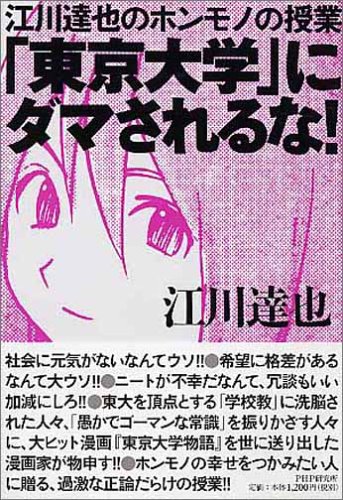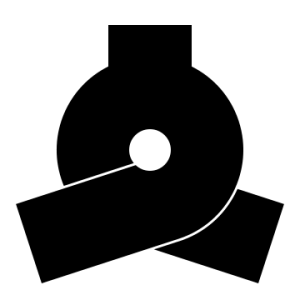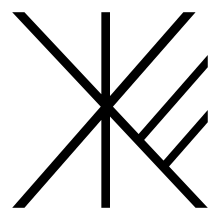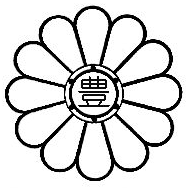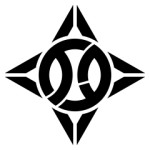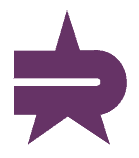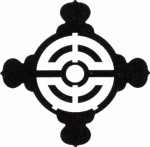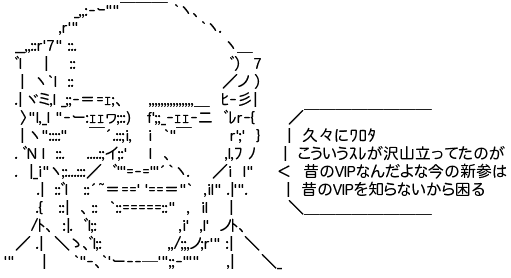新宿区の由来
江戸幕府が開かれた1603年の翌年には日本橋を起点として五街道が定められた。そのうちの一つであった甲州街道 は日本橋から甲府への幹線だったが、日本橋から最初の宿場であった高井戸までの距離が長かったことで、その高井戸までの間に新しく宿場を設置したい ということで現在の新宿のあたりに新しい宿場が設けられた。その宿場は信州高遠藩内藤若狭守 の下屋敷に置かれた新しい宿ということで『内藤新宿
新宿区は1947年に四谷区 や牛込区 などを前進として発足されたが、新区名として「新宿」が採用されたのはこの「内藤新宿」が歴史ある名前であることや他の地名より普遍的な名前であるという理由からであった。他には「戸山区」「武蔵野区」「山手区」「早稲田区」などといった区名の候補があったという。
新宿区の紋章
新宿区の紋章とされているよくわからないマークは『新』という文字を一筆書きで勢い良く描いた ものであり、新宿区が未来に向かって堅実に発展していく意志を表しているという。ちょっと『新』には見えませんが…。
世田谷区の由来
「世田谷」の語源については諸説ある。瀬戸 」からきているという説。「瀬戸」というのは「狭い海峡 」を表す言葉で、瀬戸内海が海と呼ぶには狭い海峡ということでその名がついていることからもわかる。世田谷には当然海はないが、狭い海峡という意味から転じて狭い谷地 についても「瀬戸」と呼ばれるようになり、この「せと」が訛って「せた」「瀬田」になった。そして「せた峡 」と書き「せたかい 」や「せたかえ 」とも読まれた。谷が多いということで「せたがや」と言われるようになり、「世田谷」あるいは「世田ヶ谷」と書かれるようになる。「世」という文字については当て字 だと言われる。
また多摩郡の勢田 という地方に含まれていたということから「せた」と呼ばれるようになったという説もあり、上記の説とこの説を組み合わせたような説もある。
世田谷区の紋章
世田谷区の紋章については1956年に公募で決定された。
墨田区の由来
墨田区は1947年に向島区と本所区が一つになって誕生した。墨堤(ぼくてい) 」の「墨」と「隅田川 」の「田」から墨田区になった。要は隅田川が由来だということである。
墨田区という名前を決定するにあたって「隅田区 」という名前も候補になっていた。しかし1947年当時は「隅」という字が当用漢字ではなかった ため使用することができなかった。当用漢字は1946年に内閣によって告示されたものであり、1981年に常用漢字が告示されたことによって廃止となっている。そして隅田川は当時は荒川の本流部分の俗称であり法律上の正式名称ではなかった (1965年に隅田川に改称)、これらのことから「隅田区」とはならずに「墨田区」となった。
墨田区の紋章
墨田区の紋章は「スミダ」の頭文字であるカタカナの「ス」を3つ重ねた もの。言われてみればたしかにそうだ。
葛飾区の由来
まず「葛飾」という地名はこの葛飾区の固有の名称ではなく、この周辺の千葉県や埼玉県、茨城県を含めた葛飾郡という広い区域を示すものであった。その中央は現在の千葉県市川市の辺りであり、現在の葛飾区の辺りは葛飾西部ということで葛西 と呼ばれていた。そのため現在も葛西駅など地名や施設名にその名が残っている。逆に千葉などの地名に「葛飾」やその一部がつく地名や施設が多いのもこのため。
「葛飾」の語源については諸説あるため、明確な由来は不明。葛(くず) がたくさん繁っていたため「葛繁」とされ、それが変化したという説。
葛飾区の紋章
葛飾区の紋章・マークは葛飾(カツシカ)の頭文字である「カ 」そして感じの「力(ちから) 」を意味している。とてもシンプル。
千代田区の由来
千代田区は1947年に麹町区と神田区が合併してできた区。江戸城 千代田城 末々まで繁栄し続ける田園地帯 であるという意味を持つ「千代田村」という地名から採ったものだった。
千代田区の紋章
千代田区の紋章は「千 」の文字を鶴が飛ぶ姿に、そして「代」を平仮名の「よ 」としてその形に似せ、マーク全体が「田 」の字になっている。
目黒区の由来
目黒区は1932年に目黒町と碑衾町(ひぶすままち)が合併してできた区。
まずは「目黒不動尊 」からという説。これはこの地に古くからある「龍泉寺」というお寺が通称「目黒不動」と呼ばれているため、そこから地名が付けられたというもの。「目黒不動」というのは、五行思想の五色である「白・黒・赤・青・黄」にまつわる伝説をもつ不動尊を指す『五色不動 』の一つ。これは各所に存在するが東京のものが特に有名であり、目黒不動 の他にも目白不動 目赤不動 目青不動 目黄不動 不動レンジャー
他にはこの地方は牧場が多く、そこで飼われていた馬の毛色や目の色 が黒かったからという説。馬畦(めくろ) と呼び、それが訛ったものだというものもある。
目黒区の紋章
目黒区の紋章は合併する前の目黒町で使われていたものをそのまま引き継いだものであり、大正8年に目黒町になる前の目黒村の役場関係者によって作られた。意味がわかっていない とのこと。目 日
文京区の由来
分陽区は1947年に当時の小石川区と本郷区が合併して誕生。公募 によって決定された。東京大学 をはじめとして教育機関が数多く存在することや出版関連の会社も多いことから「文の京(みやこ) 」「文教の府 書きやすい ということから採用された。
文京区の紋章
文京区の紋章も公募によって決められた。「文 」の文字を図案化したもの。
台東区の由来
台東区は1947年に下谷区 と浅草区 が合併して誕生した。上野区 」、浅草区は「東区 」を提案。しかしそのどちらとも決められることはなく、最終的には上野の高台 である「台」の字と、上野の東側の下町 を連想する「東」を組み合わせた「台東」となった。日出る処、衆人集まって栄える場所 」というめでたい意味でも載っている。たいとうく 」と読むが、初期の頃は統一されていなかったため、高齢者には「だいとうく 」と読む人も多い。
台東区の紋章
区の紋章は「台」と「東」を組み合わせたデザイン。中の宇文が「台」外の部分が「東」を表している。目黒区の紋章と似ている。
江東区の由来
江東区は1947年に深川区 と城東区 が合併してできた区である。隅田川の東側 であるという意味と、深川を意味する「江」と城東を意味する「東」でもある。
江東区の紋章
江東区の紋章は区内の小中学校から募集 した物から採用し、一部修正したとのこと。ずばり「江東」の文字が入っているという、他の区に比べ非常にわかりやすい ものになっている。
品川区の由来
1932年に品川町、大井町、大崎町によって品川区が誕生、1947年に荏原区を編入して現在の形になった。目黒川 がかつて「品川」と呼ばれていたということからきているとされる、河口付近は古くは港 して使われており、『品』の行き交う『川』 であったことから「品川」となったとされている。
またこれ以外にも品(ヒン) の良い地形だということから「高輪」という地名に対して「品ヶ輪 」→「品川」となった説や、下無川 」から「品川」になった説、の領主が「品川氏」 であったという説、など諸説がある。
品川区の紋章
品川区の紋章は「品 」の字を図案化したもの。「友愛 」「信義 」「協力 」の3つからなる推進機の形になっており、前身と勤労 を象徴している。
江戸川区の由来
区名の由来は区内を流れる「江戸川 」からそのまま採ったもの。区名を決める際に「松江」という地名から「松江区」という案もあったが、知名度が低いため採用されなかった。江戸に通ずる川 」という意味から、「江戸」は江(川)の戸(入り口)という意味だとされる。
江戸川区の紋章
「江戸川」の頭文字である「エ 」を鳩 として図案化したもの。発展と平和を象徴しており、円形は区民の協力と融和を示している。
渋谷区の由来
渋谷区は渋谷町、千駄ヶ谷町、代々幡町が合併して誕生、当時最も発展していた渋谷町 から区の名前が採られた。塩谷(しおや)の里 」と呼ばれており、「しおや」が「しぶや」に変わったという説。渋谷権介盛国 」という賊を捕まえた。これにより河崎重家に「渋谷」の姓が与えられ、その領地が「渋谷」という地名になった説。シブ色 」だったことから「シブヤ川」と呼ばれた説。
渋谷区の紋章
渋谷区の紋章は昭和31年に区民からの公募で決められた。
大田区の由来
大田区は1947年に当時の大森区と蒲田区が一つになって誕生した。大 森」と「蒲田 」から一文字づつとって命名された。
大田区の紋章
大田区の紋章は区民から公募したもので、区名と同じく「大」と「田」の文字を図案化 したもの
中野区の由来
中野区は1932年に中野町と野方町が合併して誕生した。この際「中野 」と「野方 」から一文字づつ採ったという説と、単純に「中野」から採ったという説がある。中野郷 」から来ている。これは武蔵野の真ん中にある郷 という意味である。また、善福寺川と妙正寺川の中の郷という意味もあるという。
中野区の紋章
中野区の紋章は昭和15年に区民からの公募で決定。「中」と「の」 を図案化したもの。
杉並区の由来
杉並区は1932年に杉並町、和田堀町、井荻町、高井戸町の4つの町から誕生した。領地の境界線 として青梅街道に沿って杉並木 を植えたことが始まりとされています。明治時代の前にはこの杉並木はすでに無くなっていたようですが、その後も村の名前として残り、杉並町、そして杉並区となった。
杉並区の紋章
杉並区の紋章は「杉の木」の文字を図案化したものえ、昭和27年に制定された。
豊島区の由来
1932年に巣鴨町、西巣鴨町、高田町、長崎町の4町から豊島区が誕生。もともとこの4つの町があったのが北豊島郡であったため「豊島区」という名称が採用された。多くの島(州) があった事が由来となっている。島が豊かにあったということから「豊島」
豊島区の紋章
区の紋章は豊島の「豊」の文字の周りには東京都の紋章である六方に伸びる亀甲模様、そしてその外には菊の花が描かれている。
荒川区の由来
1932年に南千住町、三河島町、尾久町、日暮里町が合併して荒川区が誕生した。荒川 」が由来となっている。現在の隅田川 は昭和39年まで荒川と呼ばれていた。つまりは区名は現在の隅田川から付けられたとも言える。荒ぶる川 」ということでその名がついた。
荒川区の紋章
区の紋章は上部が「ア」中心の水平線と下部が「ラ」中心の三本線が「川」で「アラ川」となっている。わかりにくいがよく見れば確かに。
板橋区の由来
1932年に板橋町、上板橋町、志村、赤塚村、練馬町、上練馬村、中新井村、石神井村、大泉村の9つが合併して板橋区が誕生した。木の橋 のことを「板橋」と読んだという説が有力とされている。また、「イタ」は崖や岸といった意味であり、崖の端にある土地 であることを意味しているという説もある。
板橋区の紋章
区の紋章は「イタバシ 」の4つのカタカナを図案化したもの。中央の円が「イ・タ 」四方に「ハ」がが4つということで「ハシ 」となる。野球のボールのようにも見える。
練馬区の由来
1947年に板橋区から練馬町、上練馬村、中新井村、石神井村、大泉村が分離して誕生した。馬を集めて調練した地 であったことから「練馬」となった説。ねり場 」と呼ばれたことから説。根沼(ねぬま) 」と呼ばれていた説。乗潴(のりぬま) 」という宿駅が「ねりま」となった説。
練馬区の紋章
区の紋章は「ネ」の文字と「馬のひづめ」を図案化したもの。なんかかわいい。
足立区の由来
「足立」という地名の由来には諸説ある。葦が立つ 」というところから「葦立」「あしだち」「あだち」となったという説。台地 」を意味する「たち」という言葉に接頭語の「あ」 がついて「あたち」となった説。日本武尊 が立てるようになったという伝説からその名がついたという説。阿太知 」書かれていたものを置き換えたものであるという説などなど。
足立区の紋章
足立区の紋章は昭和33年に公募によって決まったもの。「足立」の文字を図案化している。落下してる人のようにも見える。
中央区の由来
1947年に日本橋区と京橋区が合併して中央区が誕生した。東京のほぼ中央 に位置しているからというそのままの由来である。
中央区の紋章
中央区の紋章は日本橋・京橋の欄干擬宝珠 (らんかんぎぼし)を図案化したもの。欄干擬宝珠というのは橋の装飾のこと。橋というのは古来から文化経済の発祥とされていることから。図中央の円は日本と東京の中心 を示している。
港区の由来
1947年に芝区、麻布区、赤坂区が合併して港区が誕生した東港区(とうこうく) 」という名称に絞られ、そうなる予定でもあったが、「東京都東港区(とうきょうととうこうく
港区の紋章
区の紋章は昭和24年に制定された。「港区(みなとく)」の「み 」を図案化したものである。
北区の由来
1947年に王子区と滝野川区が合併して北区が誕生。東京の北部 にあるから。しかし「城北区 」や「京北区 」という案もあったそうで、最終的には東京における位置を示す「北区」に落ち着いたとのこと。
北区の紋章
北区の紋章は「北」の文字を図案化したもの。円に翼が生えたようなデザインで、ダイナミックに躍動する姿を表している。
久々にワロタは文字通り久々にワロタ時に貼られるAA
久々にワロタの元ネタ
AA部分とセリフ部分については元ネタが別である。モーニング娘。(狼)板 で使われていた下記のコピペを改変したもの。
久々にワロタ
昔は顔文字つかっただけでGM池とののしられたもんだ
祭りがあれば無意味に盛り上がれ、それが昔の狼だったのに
このコピペの最初の部分を改変したものがVIP板で使われていた。銀河英雄伝説 』に登場するハイドリッヒ・ラング というキャラクターである。もちろんこのセリフとこのキャラとは全くの無関係である。
2005年頃にVIP板に新参が大量に入ってきたことでVIPクオリティの低下が危惧された際に、古参が新参を嫌がり「VIP終わったな」等としていたことを揶揄する意味で多数貼られていたAAである。
読み : ネダルナ、カチトレ、サスレバアタエラレン
「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」は自分の求めるものはねだるのではなく、自分の力で勝ち取る努力をしなさい、という意味の格言である。
「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」の元ネタ・意味
「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」はアニメ『交響詩篇エウレカセブン
第2話「ブルースカイフィッシュ」で主人公のレントン・サーストンはリフボードで空を飛ぶ際、小さい頃に姉・ダイアンから聞いた「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」という言葉を思い出し、「アーイ キャーン フラーーーイ!!!」と叫びながら、初めてリフで空を飛ぶことができた。この格言は父のアドロック・サーストンが最後に家を出た時に姉のダイアンに遺した言葉 である。
今までリフで空を飛ぶことができなかったレントンが、父の遺した言葉を力にしてリフを成功させた。そして、リフで空を飛ぶことができたレントンは心の中でこう叫び、難易度の高い技・カットバックドロップターンを成功させた。
待ってちゃダメだ、ねだってちゃダメだ、俺は今・・・勝ち取りに行くんだ!!!
「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」の元ネタの元ネタ
「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」はエウレカにおけるオリジナルの格言であるが、『新約聖書 −マタイによる福音書(マタイ伝 )』の7章7節に記されている以下の言葉を元ネタにしていると考えられる。
求めよ、さらば与えられん
この言葉は「神に祈り求めなさい、そうすれば神は正しい信仰を与えてくださるだろう」 という意味である。
「ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられん」とは少し意味のニュアンスが異なっているが、与えられるのを待つのではなく、自分から求めて動くことが大事 であるという意味では、言わんとしていることは同じである。
ゲッコーステイトのリーダー・ホランドも師であるアドロック・サーストンからこの言葉を聞き、大事にしていた。
「しゃべる机」は人間と会話することができる机のこと。
しゃべる机とは
しゃべる机というのは新聞社などの「デスク」のことである。
主に日刊ゲンダイや夕刊フジといった夕刊紙において、記者と「デスク」との会話形式で記事が書かれている
デスクというと言うまでもなく英語の「desk」つまり「机」であり、さも机が喋っているかのように思えるというわけである。こういった夕刊紙ではありもしない妄想を書き連ねていることも少なくなく、とくにこういった記者とデスクの会話形式になっている記事に関しては実際にデスクとの会話などなかったにも関わらず、そういった会話があったかのように書かれていることが多い。
記事の内容にも信ぴょう性がないため、こういった記事に対しては「机が喋った 」「また机が喋ったのか 」「ま机喋 」などと書かれる。
デスクってなんだ
そもそもこの「デスク」というのはどういう人なのか。デスクは新聞社において記事の取材や編集を統括するポジションの人間のことを指し、記者が書き上げた記事の内容を最初に確認する人間でもある。誤字脱字をチェックしたり内容に駄目だしをしたりする。
しゃべる机は実在していた…。リビングのおともだち つくえちゃん
「ハーレムシェイク(Harlem Shake)」は2013年の2月頃から広まった動画シリーズを意味する。Do The Harlem Shake! 」の掛け声を合図に全員が踊り出すのがお決まり。
ハーレムシェイク(Harlem Shake)の元ネタ
ハーレムシェイクの元ネタは日本在住のヴロガー・Filthy Frank(フィルシー・フランク)氏 DO THE HARLEM SHAKE (ORIGINAL) 」。使われている楽曲はフィラデルフィア出身のDJ・Baauer(バウワー) の『Harlem Shake』。本曲は動画がきっかけで爆発的に知名度を上げ米iTunesシングルチャートで1位を獲得。
これがブームの元となったオリジナルの「ハーレムシェイク」。ピンクの全身タイツを着ているのがフィルシー・フランク氏
オリジナルと同日に投稿された「The Harlem Shake v1 (TSCS original) 」。本動画が「ハーレムシェイク」を広めるきっかけになった。本動画では冒頭で一人だけ踊り途中から全員が踊りだす。現行の「ハーレムシェイク」はこの動画を元にしていることが分かる。
アメリカのテレビアニメ『ザ・シンプソンズ』バージョンまで作られた。
LMFAO のRedfoo(レッドフー)もヴァレンタインに恋人のテニスプレイヤー、ビクトリア・アザレンカ(ヴィカ)に向けて「ハーレムシェイク」を制作
ノルウェー陸軍まで「ハーレムシェイク」に参戦。オリジナルを超える再生回数を記録
他にもGoogleやIntelオフィスで撮影したバージョンもある。